
GWももう終わり。
喧騒を離れた海辺の町から
ビル群建ち並ぶ都会の町へ帰る時、
それは非日常の世界から
日常の世界に戻るという事。
いつものメンバーと仕事が待ってるね。
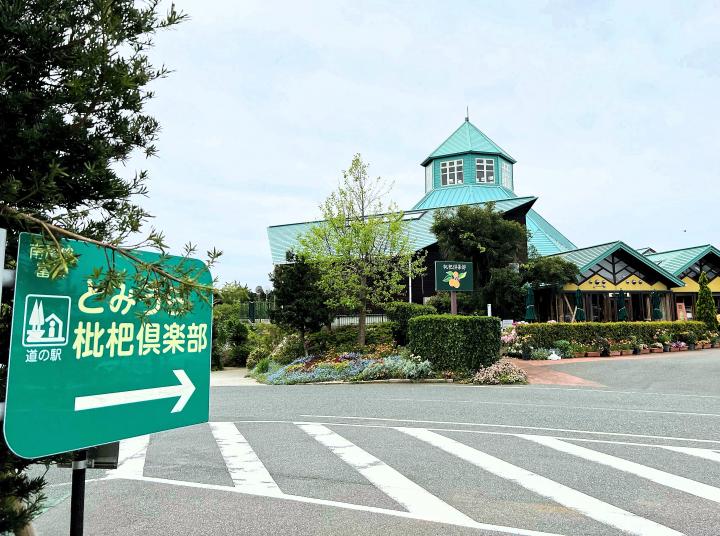
バスツアーでお馴染みの『道の駅』巡りも
海の幸、山の幸、スイーツ等の食べ歩きも
時勢柄 極力人混みを避けたいために
足が遠のいてしまった。
また、今年は猫も一緒に来ているから
長時間の留守番をさせたくないせいで
なおのこと外へ出ない。

朝から晩まで
ずーっと
四六時中
猫とべったり🐈💕

それはそれで楽しい🐈💕
猫も非日常の環境にすぐ慣れて
磯の香りや草木の香りをクンクン
小鳥🦜や蝶々🦋が飛ぶのを凝視してる。
遊び放題、甘え放題、わがまま言い放題😼✨
【猫の嗅覚・視覚の話】
猫は人間の1万倍~10万倍の嗅覚がある。
空気中の臭い物質の濃度が
人間が感知できる最低濃度の
1万分の1の濃度でも分かるそうだ。
嗅ぎ分ける能力は人間とは
比較にならないというわけだ。
また、基本的に近くも遠くも
同じように見える人間と違い、
猫の視力は2m~6m範囲のものに
一番ピントが合うようにできている。
理由は、ネコ科の動物の狩りの範囲が
この距離だからだそうだ。
猫は元々夜行性なので、夜、目が利く。
網膜の裏にタペタム層という細胞層があり、
わずかな光でも、光さえあれば反射して
視神経に伝え見ることが出来る。
猫の場合、人間の1/6の光量でも
物を見分けることが可能である。
暗いところでフラッシュをたいて
猫を撮影すると、時おり猫の目が光って映るが
それはこのタペタム層があるからである。
光に敏感なのだ。
昼間は1本の線のように縦に瞳孔を細くして
眼球に入ってくる光の量を調整する。
昼間の強い光を遮ぎるのである。
縦長の瞳孔を持つ動物は、
縦方向にレンズを絞って
縦に広くピントを合わせる。
さらに左右の目を使って
立体的に物を見ることで、
対象物との距離感を捉える。
待ち伏せをして狩りを行う動物にとって、
獲物との距離感を掴むことは重要な要素だ。
猫のように木の上など高い場所や
狭い藪の中で獲物を待ち伏せする動物にとって、
縦に広くピントを合わせられることは
理にかなっていると言える。
(PetSmile【面白ねこ雑学】より)
海辺の町、田舎の家に来て
磯の香りや草木の香りを嗅いだり
小鳥や蝶々を凝視して
野性に目覚めたうちの子😼✨
すっかり奔放に振る舞うようになった。
もう田舎と都会の匂いの違いを
ちゃんと嗅ぎ分けて感じとれるはず。
今日はコンクリートやアスファルトの匂いの
する場所、東京に帰るよ。
すんなり日常生活に戻ってくれると
いいのだけど…🤔✨
そういえば💡✨
話はぜんぜん変わるのだけれど💡✨
昨日食べたアイスが
蓋を開けたら
こんな事になっていた😃✨

ハート形♥️🧡💛💕
なんかいい感じ♥️🧡💛💕
たまたまだけど、アイスがこんな風に
なってるの、あまり見たことない♥️🧡💛💕
思わずパチリ📸✨
最後まで読んで頂きありがとうございます😊💕


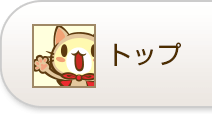

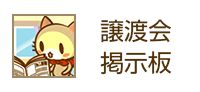


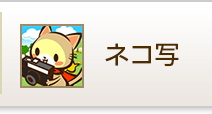
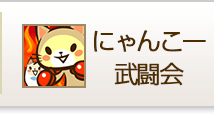
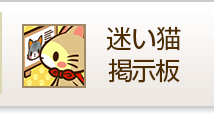
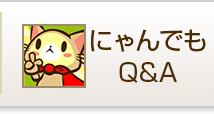

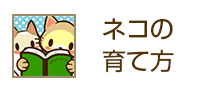
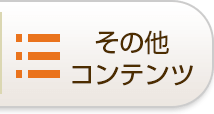


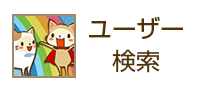


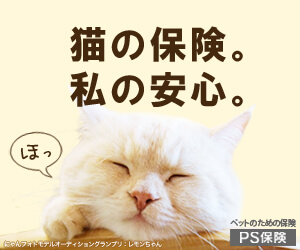






















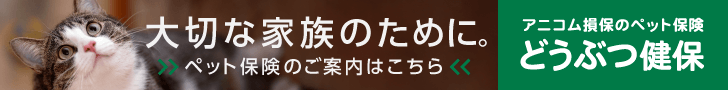
 24
24
最近のコメント